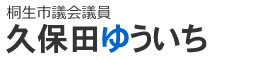デジタルサイネージ98台導入によるエリアマネジメント。全国商店街青年部研修会in那覇市 その②
商店街創生セミナー2日目は前日と同じくオリオンホテル那覇を会場に開催されました。1つ目の研修は「日本最大規模 計98台のデジタルサイネージを活用したエリアマネジメント」と題して、那覇市国際通り商店街振興組合連合会の和田紘明 理事にお話をいただきました。那覇市は人口約31万人の云わずと知れた沖縄県内最大の都市。観光客数は年間966万人(令和6年)となり、国際交流都市でもあります。那覇市の中心市街地には法人格の有無を問わず、商店街組織が約30団体組織され活動しているそうです。
戦災復興と共に発展した国際通りは奇跡の1マイル(1.6km)と言われた沖縄を代表する繁華街であり、この周辺に中小の商店街などが点在しています。これまでの国際通りの取組みとしては、毎週日曜日の12時から18時までを封鎖してコミュニティバスのみが運行できるトランジットモール型のイベント「トランジットマイル」や、国際通りを交通規制して多数のエイサー踊り隊が演舞を披露する「一万人のエイサー踊り」などがありますが、現在はイベントで集客するまでもなく多くの歩行者量があり、それぞれイベントのあり方について見直しの意見も出ているとのことでした。


コロナ禍が落ち着き観光都市として活況を呈する国際通りが抱える問題としては、県外からの出店も多くお互いの顔が見えない商店街になっていること、次世代の担い手不足、観光客の増加による不法投棄問題や違法看板、路上喫煙などの環境整備などがあげられるとのこと。「街の未来を考えるため、まずはコミュニケーションの活性化から」「敵を作って戦うのではなく、仲間を増やして共に成長する商店街に」と和田さんが語っていたのが印象的でした。
そんな課題を払しょくするための取組みとして、中心商店街エリアで商店街や通り会の垣根を越えて活動する「なはまちぐゎー青年部」が発足しました。ちなみに、沖縄の方言で市場や商店街のことを「まちぐゎー」というそうです。組織の形態を問わずに参加でき、交流に重きを置いている活動形態は若い世代に非常に合っていると感じます。ぜひ群馬県内の青年部の立ち上げに当たっても参考にしていきたいと思います。
そんな中、エリアマネジメントの検討に当たって平成27年の資料を参考に新規の取組みが立ち上がりました。それは「国際通りまち活性化協議会」で検討された、街頭に設置してあるバナーフラッグの公告としての運用を商店街で行う実証実験の構想です。当時は事業化に至らずに立ち消えになってしまいましたが、沖縄電力が変電地上機器の有効活用を検討しているという話から、フラッグをモニターに変えて事業化することを構想し、エリアマネジメント共同体を立ち上げるに至っています。事業主体は沖縄振興エリアマネジメント推進共同体で、参加者は那覇市国際通り商店街振興組合連合会と沖縄電力株式会社、株式会社琉球新報社の3者です。1.6kmの沿道にキューブ型49台(連合会管理)、地上機49台(沖縄電力管理)の計98台を設置。収益はエリアマネジメントに活用され、不法投棄などの様々な課題解決に活用されているそうです。事業費は4年間で15億円と高額ですが、国県市を通じて2/3は補助金となっています。とは言っても、やはり共同体が自己負担する額は多額であり、安定した広告料収入があってこその事業だと思います。その点、国際的な観光都市の目抜き通りである国際通りのポテンシャルがあってこその取組みであるとも感じました。

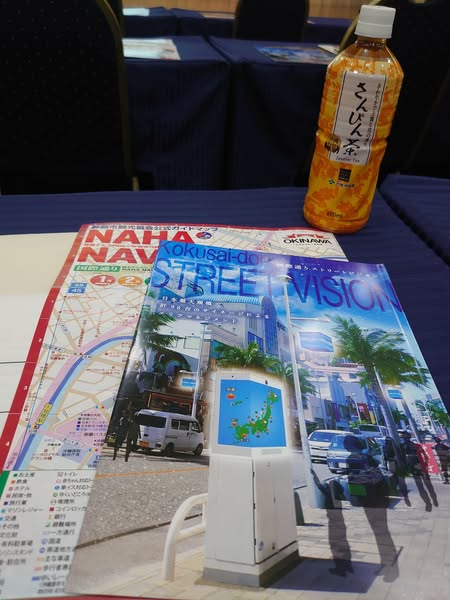
放映する情報は民間事業者等から提供される有料広告の他、公共情報として那覇市や沖縄県が発信する防災・災害等に関する情報や観光やイベントの情報も共有されています。その他、緊急時防災情報 LアラートやJアラートが発出されると自動で情報が放映されてアラーがなるなど、街の防災インフラとしての機能も備えています。
その他、AIカメラを設置して歩行者量や通行車両数を可視化することで広告効果などもデータで可視化できるなど、様々な機能が備わっており、今後は防犯カメラの機能も実装予定とのことで、非常に多くの機能を持ったプロジェクトとなっていることがわかりました。
モニターの設置というと広告機能で収入を得るといった印象も受けますが、和田さんがおっしゃるように「エリアマネジメントをするということを重視」している姿勢を強く感じます。自分たちのまちづくりを自分達でしていくための仕組みづくりを主体的に取り組んでいる国際通りのプロジェクト。このままの規模で桐生市に持ち帰るのは現実的ではありませんが、同様の思考を取り入れたエリアマネジメントに取り組んでいくことの必要性を強く感じた次第です。つづく