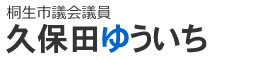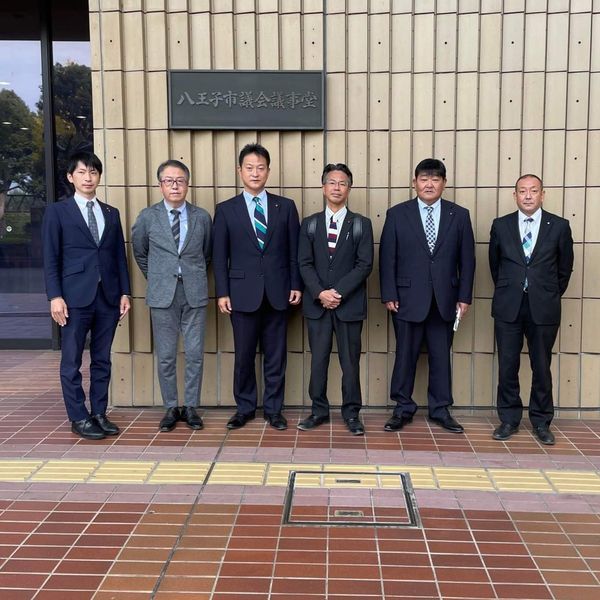桐生の原料で作る「寅印」の桐生和紙
少し前の話題ですが、今月初めにPENSEE GALLERYにて開催された展覧会「桐生和紙の仕事【寅印お披露目】」に寄らせていただきました。桐生市梅田町の清流に育まれた桐生和紙の伝統をただ一人受け継ぐ橘さんによる展示会です。

会場には新たに立ち上げた「寅印」ブランドの桐生和紙が並びます。私は巻紙と冊子「寅草紙ができるまで」を購入させていただきました。おそらく巻紙を手にするのは人生初。使い道は決まっていませんが、短く切ったり、長く使ったりと自由度が高く、使い方を想像するだけでもワクワクします。
寅印の由来について、展示や冊子の中で紹介されていました。江戸時代からの流れをくむ桐生和紙は、原料の楮は当時全て地場のもので賄われていましたが、現在は原料の大部分を購入しているとのこと。桐生での原料作りの技術も継承をしながら、少量ずつでも確実に作り続けていきたい、その様な想いから「寅印」ブランドを立ち上げたそうです。「寅印」の名前の由来は明治まで遡り、往時は桐生に20戸ほどの漉き屋があったとのことで、橘さんの祖父である六代目の冨吉さんによれば祖父の寅吉さんが手掛けた紙は「寅印」と呼ばれ、他の桐生紙よりも高値で取引されたそう。当時「寅印」は桐生和紙にとっての高品質な和紙を保証する証となっていたようです。

桐生川の清流を活かした「桐生和紙」の技術を継承し、そして原材料も桐生にこだわって和紙づくりに取り組む橘さんの存在は、桐生が継承していかなければならないかけがえのない宝だと改めて感じました。