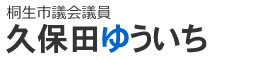二度と悲しい事故を起こさないために。園バス置き去り防止の実証実験

昨日は桐生市内の幼稚園で実施されている園バス置き去り防止システムの実証実験の視察及び、開発メーカー様との意見交換の機会をいただき、子どもの事故予防地方議員連盟の県内有志メンバーで参加してきました。
昨年9月に静岡県の認定こども園において発生した3歳児が通園バスの中に取り残され死亡するという痛ましい事故は記憶に新しいところ。一昨年には福岡県でも同様の事故が起きており、事故がある度に国からの注意喚起の通知が出されていますが、残念ながら事故は繰り返されています。子どもの命にかかわる重要な問題であり、もう二度と事故を起こさない抜本的な対策が急務です。
今回の視察では、置き去り防止システムの基本的な考え方や、国や県の補助内容などの情報交換を行い、その後、実際のバスを用いた基本フローのデモンストレーションの見学を行いました。対策の本質的な課題などについて理解を深める良い機会になったように思います。



今回の視察を通じて、機械が監視することで防げる事故はあるかもしれませんが、それに慣れてしまったときに注意力が衰えてしまうのではないか、そんな恐怖も感じました。人の命がかかっているシステムに万が一でも不具合は許されませんが、何事も100%はあり得ません。最終的には人による確認が重要であり、それらをサポートするためにシステムがある。そのような視点に立った時、現在の内閣府のガイドラインの想定はまだ完璧とは言えないのではないかとも感じた次第です。
また、行政側の支援の問題としては、イニシャルコストには補助が出てもランニングコストには補助が出ないことが挙げられます。通信費などを伴うシステムを導入した場合、結果体に送迎バスを使う保護の負担増加や園の経営に負担がかかってしまいます。また、同じ園バスでも園外活動などのためにバスを所有している園も多く、これらは義務化や補助の対象には入っていません。
今回の実証実験はメーカー側が開発の方向性や課題を確認し、今後の製品化に活かしていくためのもの。単純に機能を満たすだけなら機械的に作れるかも知れませんが、この現場のスタッフの皆さんからは「二度と事故を起こさない」という強い決意を感じました。
機械に頼ることで人間の注意力が下がり、置き去り防止システムを導入しているのにも関わらず事故が発生してしまう。そんな悲しいニュースが発生しないよう、義務化前の今だからこそ本質的な議論をしていく必要がありそうです。
貴重な機会をいただいた園関係者の皆様、及びメーカースタッフの皆様に心より感謝申し上げます。