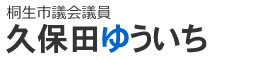コロナ禍での交流のあり方。青少年問題協議会
本日午前は青年の家にて開催された「桐生市青少年問題協議会」に参加させていただきました。この協議会は昭和28年施行の地方青少年問題協議会法に基づき設置されているもので、青少年の指導、育成、保護などに関する対応を審議する協議会であり、教育長や関係行政機関の職員、桐生市内の青少年関係団体、市議会議員など約20名で組織しています。

ここ数年はコロナ禍で対面の会議が設けられない時期もありましたが、昨年度からは対面での会議を再開。ただ集まって話し合うだけでなく、具体的な対策に結びつけていこうということで、専門部会での詳細な議論を重視した運営にシフトしてきています。
今回は全体会の中で、桐生市いじめ防止対策についてなどの報告があり、その後「子ども対策」と「家庭・地域対策」の2つの専門部会に別れて詳細に議論が行われました。
私が参加させていただいた「子ども対策部会」の中では、臨海子ども会が開催3日前に中止になるなど、感染症の影響で様々な事業が影響を受けている現状を確認した上で「コロナ禍でイベントが中止になったりすると、準備をしてきた子ども達の喪失感が大きい」「様々なイベントが中止となり、地域住民や保護者との繋がりが途切れ、声が届かない現状がある」「縮小しながらでも、回数を増やすなど、できる限り対面の機会を設けていくことが必要なのではないか」などの意見が出され、コロナ禍でのイベントのあり方や、コミュニケーションの機会を奪わないようにするためにはどうしたら良いかなどについて活発に意見が交わされました。
本協議会の任期は2年、会議は全4回と機会は限られていますが、答申を無理矢理作るのではなく、今ある課題を挙げるなかで具体策に結びつけていくことができたらと思います。参加された皆様、たいへんお疲れ様でした。