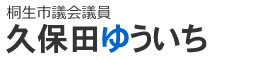自治体が美術館を持つという意義は。全国若手議員の会 公式研修in大阪
本日は全国若手議員の会 関西公式研修に参加。研修1つ目は「中之島美術館の開設までの経緯」と題して大阪市経済戦略局文化部文化課 博物館支援担当課長の平野いずみ様にお話をお伺いしました。

大阪市では、元々あった特色ある博物館・美術館5館を一体的に運営して大阪市の一つの魅力にしていくことを目的に、平成31年に大阪市博物館機構に運営を移行。各館の連携強化を図っています。後に開館した大阪中之島美術館を加え、現状では大阪市から全6館分の運営費を約22億円支出しているそうです。
大阪中之島美術館の構想の始まりは古く、昭和58年の市政100周年記念事業基本構想の一つに位置付けられたことに始まり、昭和63年に近代美術館構想委員会が発足しています。コレクションあっての美術館ということで、平成元年に大阪市美術品等取得基金(30億円)を設置して美術品の収集を開始するも、財政難による構想の練り直しなどを経て平成25年に中之島に美術館を整備することを決定するに至りました。
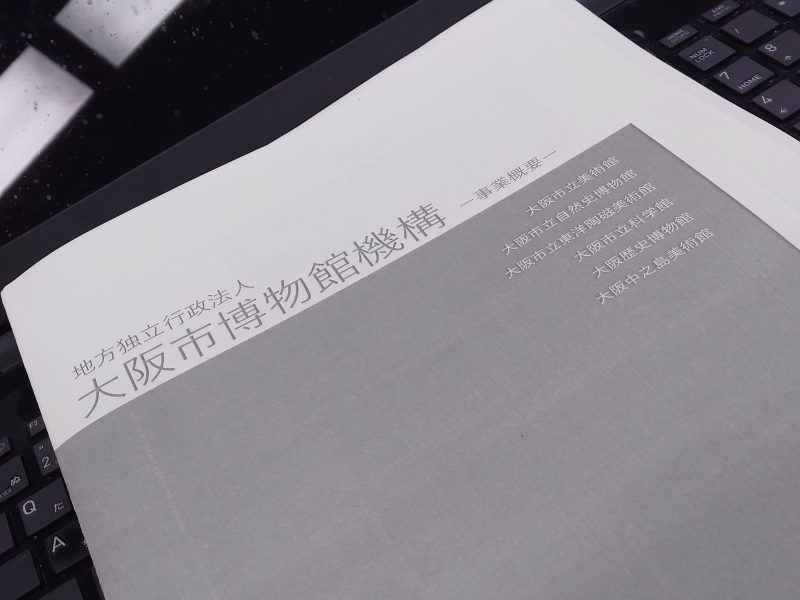
ちなみに、大阪市が現在所有する美術品は作品数で6,151点(購入 1,155点/寄贈 4,996点)、評価額で約267億円(購入 約155億円/寄贈 約112億円)とのことです。アメデオ・モディリアーニの作品を19億円で購入するなど、大阪市による直接購入している例もありますが、寄贈された作品の点数も多く、美術館とういう受け皿があることにより美術作品の流出を抑えられる効果もあるのではないかとも感じるところです。
大阪中之島美術館は大阪市が保有する第一級のコレクションを活かした国内トップクラスのミュージアムを目指すために計画され、紆余曲折を経て令和4年2月2日開館しました。事業方式はPFI方式を採用しており、運営権を地方独立行政法人(機構)から株式会社中之島ミュージアムに渡しています。大阪市の負担としては、機構を経由して株式会社に対してサービス対価を約3億3千万円、作品購入費用として毎年5,000万円、機構からの館長・学芸員を派遣するための人件費として1~1.5億円をそれぞれ支出しているそうです。運営をPFI方式にして民間活力を導入するなどの努力はされていますが、やはり博物館や美術館などの施設は収益性のある事業ではないため、これらの数字を見ると美術館の維持管理には大きな予算がかかるということを改めて実感します。

桐生市では公益財団法人が運営する大川美術館に毎年約3千万円を支出していますが、市立美術館を開設するためには更に多くの予算が必要と考えられます。今年度、大川美術館に対しては桐生市からの補助金や民間からの寄付などが行われ、改修工事が開始される見込みとなりました。残念ながら桐生市には美術館や博物館などの文化施設がない状況ではありますが、大川美術館がある価値を捉えながら、桐生市が所蔵する文化財や美術品の所蔵・展示の在り方についてしっかり議論していくとが必要だと思います。