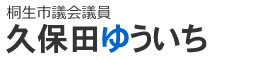全国の商店街青年部が集う意味。指導者研修会in熊本 その①

昨日今日と2日間、全国商店街青年部指導者研修会に群馬県の青年部長として参加させていただきました。会場は人口70万人を数える政令指定都市、熊本県熊本市です。70万都市と言っても、県全体の人口は群馬県より少ない170万人であり、人口規模と半数近くが県庁所在地に集中しているという構造は宮城県に似ていると感じます。商店街は総じて大規模で、3階まである大規模なアーケード街には昼夜人の流れが絶えません。
さて、この指導者研修会は全国の商店街青年部が集い、今後の地域経済を担う若手経営者及び後継者を対象に、商店街活性化に資する知識と繋がりづくりを行うことを目的としており、今回も全国から約80名が集まりました。
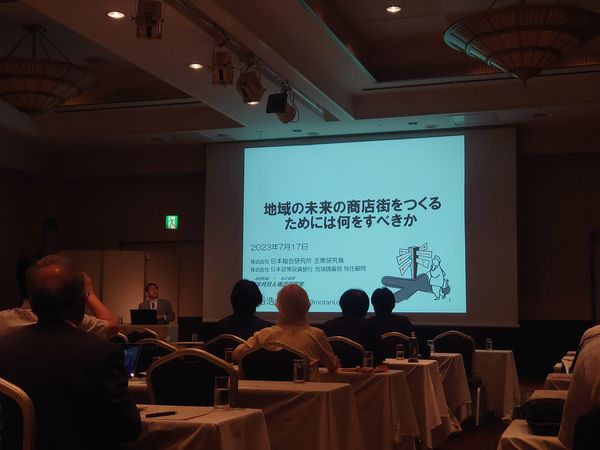
初日となった7月18日(火)は(株)日本総合研究所 主席研究員である藻谷浩介 様による基調講演「地域の未来の商店街を創るためにはなにをすべきか」からスタート。昭和の日本で商店街に人が集まった要因、平成の日本で商店街が衰退した要因を紐解きながら、商店街のような場が令和に再生されていくとすれば、その要因はどのようなものかを考察していく内容です。これまでの都市の拡大により、低密度開発地の経済ポテンシャル低下、徒歩&公共交通の再評価、チェーン店に勝つローカルビジネスが増えていること、“共生欲求”の再評価などを踏まえて、これまでのまちづくりとは逆向きのトレンドが起こっていくことを先回りして捉えていくことの重要性をお話しいただきました。商店街の地権者がこの新たな風に乗るには、旧商店街に低層住宅を増やし、シャアオフィスやカフェを入れ、学校などの再導入を図ること、車がなくても生活できるモデルを商店街周辺で確立して発信していくことなど具体的な事例もお示しいただき、これまでの常識に捕らわれないチャレンジが必要だと改めて感じます。
また、興味深かった話は地域内でのGDPのお話し。つまり、地域内でどれだけ付加価値を生むことができたかが重要だということです。シンプルに言うとチェーン店やショッピングモールに支払ったお金は地域外に出て行ってしまう。地域外に出ていくお金を減らすためには地産地消が重要なテーマとなります。一例では、地域住民1人が年間に180万円消費すると、その1%(1.8万円)が地元産品消費に回れば10万人当たり18億円が地元に回る、これは給与+福利厚生費200万円/人の雇用900人分に相当する。同様に、中小零細事業者1社の年間経費を1億円とすると、その20%(2,000万円)が地元に落ちれば100社当たり20億円が地元に回る。これは雇用1,000人分の額に相当する。これらの価値の中心を商店街に置き、商店街での消費が地元への投資というトレンドに持って行くことが、地域の中での商店街の意義付けとして非常にすっきりするし、持続性もあると感じたところです。

続いて、熊本県八代市のタウンマネージャーである櫻井力助 様のお話しです。八代市には4つの商店街振興組合の連合会として「まちなか活性化協議会」が存在するとのことで、そこにUターンで櫻井さんがタウンマネージャーに就任してから、商店街の再生に取り組んできた過程をご説明いただきました。当初は新しい取り組みに反対する商店主等がおり、最初の3年間は関係性づくりに専念したこと、7,000名にアンケートを実施して商店街に望むことの項目への回答がほとんどない現実などに向き合いながら、危機感が共有され街の声も変わってきたことなど、具体的な体験をご説明いただきました。人手不足解消の事例としては、市内に7校ある高校から年間で約120名を受け入れ、費用面でもたいへん助かっているそうです。また資金面に関しては、屋台6台を制作して稼働させ、それらを貸し出して月15~20万円の収入になっている事例なども面白い取り組みだと感じます。現在は商店街の機能を転換して福祉に強いまちづくりにシフトを目指しているそうです。八代市の人口規模は12万人ほど。桐生市とほとんど同規模の街での事例、ぜひ参考にしてみたいと思います。