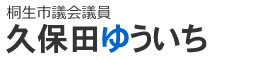子ども達を守るために。自治体としての役割【荒川区の取組】

昨日は関東若手市議会議員の会の公式研修で、東京都荒川区の「子ども家庭総合センター」について視察・研修をさせていただきました。
荒川区の「子ども家庭総合センター」はいわゆる児童相談所の機能を備えた施設で、従来のから設置されていた「子ども家庭支援センター」の機能と児童相談所機能を統合し、総合的に児童とその家庭を支援する施設として位置づけられています。


児童相談所は児童虐待等から子ども達を守る機能として、都道府県と指定都市に設置が義務づけられています。区市町村単位ですと、指定都市以外でも、中核市(人口30万人程度)や特別区などにも児童相談所の設置ができるように近年見直しが行われているところです。ちなみに、群馬県では、4つの児童相談所(支所を含む)が設置されており、桐生市を管轄するのは太田市にある東部児童相談所となっています。
今回は荒川区の子育て支援担当部長 小堀明美 様より「子ども家庭支援センター」の取組について詳細にお伺いをさせていただきました。まず、同センターは特別区で初めて設置された児童相談所であり、利用のしやすさなどを考え「相談所」とは名乗らないことで、利用時の心理的なハードルの低減に努めているそうです。実際に、児童相談所の役割は虐待の相談だけではなく、家出、不登校、しつけ、発達障害など様々な場面で子ども達を守っていく役割が求められています。
全国の児童虐待の相談対応件数は年々増加しており、令和3年度では20万件を超えたそうです。荒川区で同センターが開設されてからの相談件数は478件であり、そのうち心理的虐待が53%で、コロナ禍以降はリモートワーク等の影響もあり、心理的虐待の割合が増加する傾向にあります。
荒川区の人口は約21万人。児童相談所の設置自治体としては人口が少なく、面積も小さいことから、警察や学校等から連絡があれば直ぐに駆けつけることができる距離感が良い効果を生んでいとのことでした。荒川区の児童相談所が一時保護をして、その後に家庭の戻ることができたお子さんのうち、再び虐待等により保護された事例はこれまで一度もないとのことで、自治体のスケール感や、子ども食堂・子どもの居場所づくり関連の団体等との情報連携などにより地域で見守る仕組みづくりが上手く機能しているという印象を受けました。
毎年、児童虐待に関する悲しいニュースが絶えない中、地域でどのように子ども達を見守っていくかということが非常に重要だと感じます。児童相談所を自治体単独で設置をするということには大きなコストを要しますが、荒川区のように街の一つの機能として組み込んでいくやり方はとても参考になりました。残念ながら群馬県では児童相談所はあまり身近な施設ではありませんが、桐生市でも子育て関連の部署の集約、窓口の一元化に取り組んでいる中で、児童相談所とのより踏み込んだ連携の在り方について研究していきたいと思います。
最後に皆様にお願いです。二度と児童虐待による悲しいニュースを繰り返さないために、少しでも虐待かもと思った時には、すぐに児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」までご連絡ください。ご協力をよろしくお願いします。