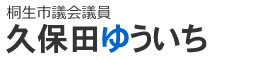現代建築保存活用見て歩き
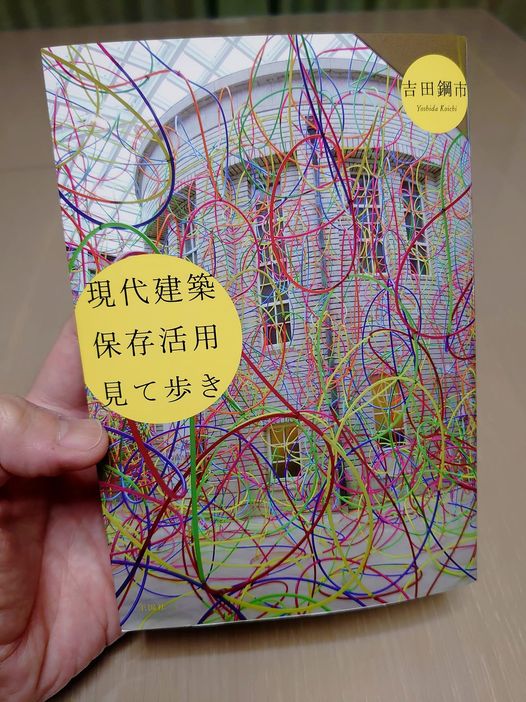
最近、タイトルと目次だけ見て購入した本です。まだざっとしか読めていませんが、私の好みのど真ん中の内容でした。現代建築と表現されていますが、本書で紹介されているのは明治期以降の近代建築。ただ一つ例外があるとすれば、江戸時代の幕末期の蔵を含む桐生市有鄰館だけです。
近代建築の保存というと、その建築の価値をどれだけ損なわないように、そして建設当時の工法や材料などをどれだけ忠実に残すことができるかが価値として語られることが多いように思います。
しかし、本書の視点は全く違います。本書で紹介されている建物たちは復元・再現・再建も含めて、形態や意匠のみを残して活用されている建物までもが全て肯定的に紹介されているのです。そのうえでのキーワードは「活用」されているかどうか。「活用」されなくなったら、その建物が存在する意味さえも無くなってしまうのです。なくなってしまったら元も子もない。たとえファザード(建物の正面のデザイン)しか残っていなくても、隣に新しい建物が増築されていても、その一部でも保存されれば建物の記憶は後世に残ります。
さて、本書では日本全国の近代建築の様々な保存活用について、そのあらゆる手法が肯定的に紹介されています。私の知る限り、このような視点の本はとても珍しいという印象です。群馬県内の建築物では既述の桐生市有鄰館の他、旧・富岡製糸場西置繭所が紹介されており、有鄰館では耐震補強の主張の少なさや、その場しのぎ感がホンモノを感じさせるとの紹介。旧・富岡製糸場西置繭所は大胆なガラスの小屋組みについての視点が記述されます。詳細については、ぜひ本を手に取って確認してみてください。
ちなみに、私の趣味の部分でいくと本書で多く紹介されている、大丸心斎橋店本館やダイビル本館などのいわゆる「腰巻ビル」がとても興味深い部分。関東ではJPタワーが有名です(本書には記載なし)。JPタワーでは東京駅前の東京中央郵便局のファザードが高層ビルの「腰巻き」となって保存されています。戦前からの「百尺規制」という高さ制限(31メートル)が昭和38年まで続き、この時代の建物を保存しながら高層化を実現するために「腰巻ビル」が全国に誕生しました。総じて批判的に語られることの多いこれらの手法についても、本書では意匠の保存と活用の部分で前向きに紹介されています。
写真も多く、読み進めていると全国の建物巡りを疑似体験するような感覚を味わえる本書。コロナ禍が落ち着いたら、ぜひこれらの建物を訪ねて旅をしてみたいですね。建築好きの方、旅好きの方にオススメです。
「現代建築保存活用見て歩き」
吉田 鋼市 著
出版元 王国社
初版 2021年11月